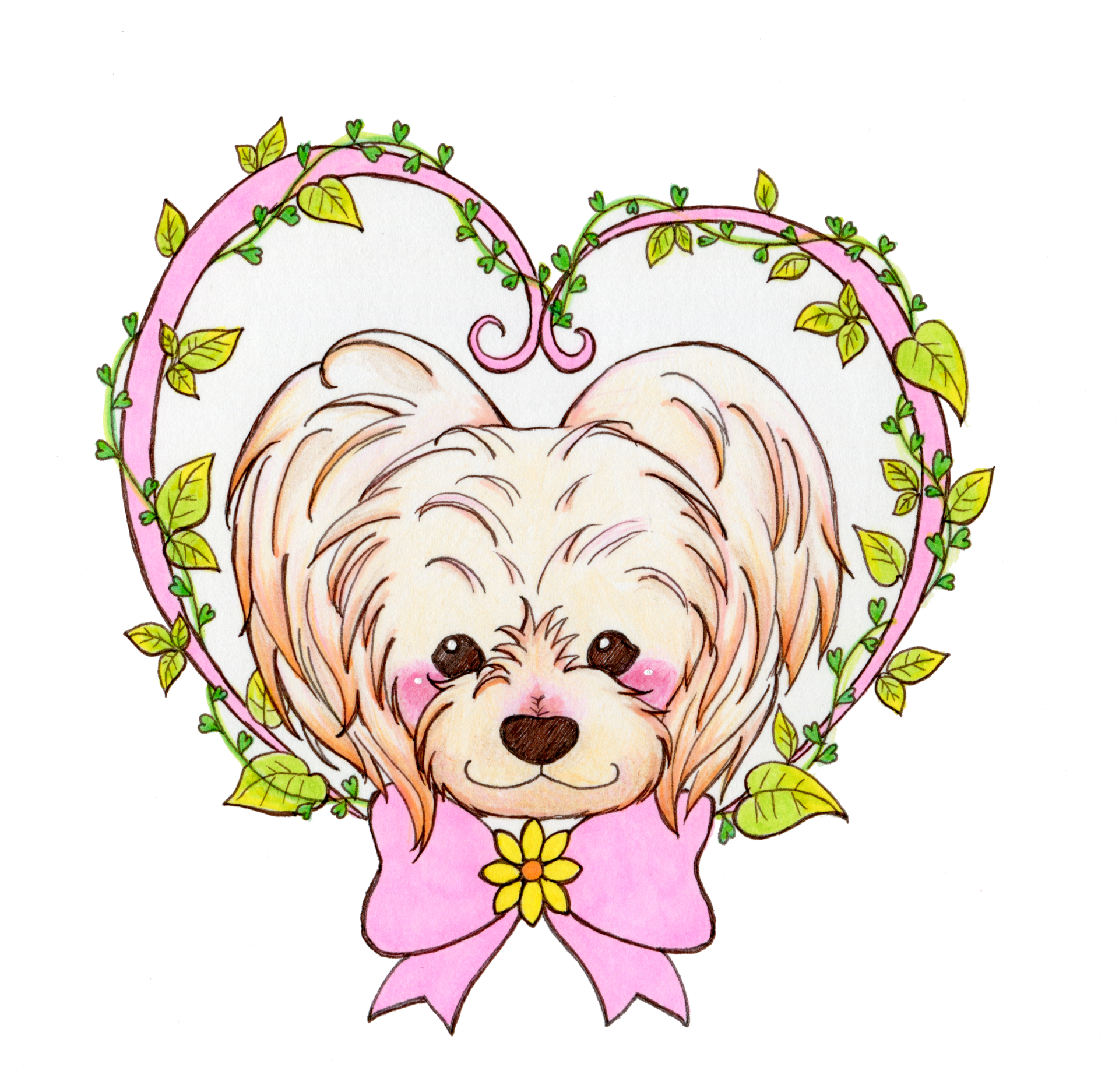Animal therapy
アニマルセラピーについて
2024年受付終了
About Animal Therapy
広義において、アニマル・セラピーとは以下の3つを総称しています。

②動物介在活動
(Animal Assisted Activity)
触れ合い・動き・気持ちも変わる
動物とのふれあいを中⼼とした活動です。レクリエーションを目的とし、動物とのふれあいによって、生活の質の向上、情緒的な安定などの効果をもたらす機会を与える活動です。 セラピー効果が生じる事は言うまでもありませんが、それは偶発的効果であり、主たる目的とはいえません。
EX)動物に触れたいと努⼒することが全⾝のリハビリに役⽴つ。
リハビリテーションへの参加が前向きになった。
共通の話題と目的ができ、友人関係がよくなった。など
③動物介在教育
(Animal Assisted Ad)
子どもたちと動物のふれあいの大切さ
情操教育の⼀環として動物を介在させる。 ⼦どもたちが動物とふれあうことにより、命の⼤切さなどを学ぶことが出来るため 道徳観を育て精神的、人格的な成⻑が促される。 また、集団でのプログラムにおいては、グループ全体の教育の質や学習意欲の向上に もつながる。
①動物介在療法
(Animal Assisted Therapy)
動物にしかできない癒やしがあります。
治療のある部分で動物が参加します。医療⾏為の⼀環として⾏うものであり、対象者の⾝体機能など向上・回復を目的とします。医師や、看護婦、ソーシャルワーカー、作業・⼼理療法⼠などが参加し、治療上のゴールを設定します。

アニマル・セラピーの効果とは
動物が人に与える効果として次の3つが考えられます。

①社会的効果
生き物との関わりこそが自立を促す
動物がいることにより話題が生まれ、会話の促進をする「社会的潤滑油効果」があります。また、動物の世話をすることにより、社会生活に適応するための練習になる等の効果が挙げられます。
さらに、障害者が、介助動物と共に暮らすことで、⾝体的、経済的独⽴を促進することにもつながる可能性があります。
②精神的効果
生きる喜び・必要とされる気持ち
動物は人々に対して⾃尊⼼、責任感、必要とされている気持ち、⾃⽴⼼や安堵感、笑いや楽しみをもたらし、ストレスや孤独感を癒すというストレスの緩衝作⽤があります。認知症の治療にも効果があるといわれており、患者の社会性を高め、介護者の負担を軽減する可能性があるといわれています。
③生理的・⾝体機能的効果
コミュニケーションは力を呼び起こす
人が動物に対して働きかけをしようとする意欲から、日常の運動や動作が多くなったり、動物に対する話し掛けにより発語が増えたりといった効果があります。そして、この意欲がリハビリテーションを⾏う際の動機付けにもなると考えられています。また、リラックスや血圧、コレステロール値の低下といった作⽤も偶発的な効果としてみうけられます。